中1息子は食塩水の問題が苦手でした。
それが、つい最近こんなことを言い出したのです。

食塩水は得意!学校のプリントがクラスで1番だった!
毎日のように食塩水のプリントをやったことで、苦手克服から得意にまでなったとは、嬉しい限り。
ということで、今回は我が家で取り組んだ方法と実際に解いた食塩水のプリント内容を紹介しておきます。
苦手な食塩水の対策
回数をこなすことが一番の近道と考えて、毎日のように食塩水のプリントを解かせました。
初めの頃は数問の簡単な問題を繰り返し解きました。
式も答えも覚える頃に次の問題を追加。
そして、半分~1問ずつ入れ替えて、ほとんどの問題は解けるけれど難しいのもある、という状態をキープして難問までもっていきました。
簡単な問題を繰り返し
食塩水は難しいというイメージが無くなるまで、全く同じ問題を繰り返しました。
初日~はこの3問だけです。
- 9%の食塩水300gの中に食塩は何gありますか。
- 42gの食塩で14%の食塩水を作ると、何gの食塩水ができますか。
- 12gの食塩と水288gを混ぜると何%の食塩水ができますか。
覚える公式は「食塩の重さ÷食塩水の重さ×100=濃度(%)」のみ。
そのうち自然と変形した公式も覚えるかもしれませんが、初めはこれだけ覚えて変形して使うのが間違いないと思います。
中学生は文字式が使えるため、分からないところにxを入れて、あとは問題文の数値を当てはめます。
そうすると答えは
- x÷300×100=9 x=9×3=27 だから 27g
- 42÷x×100=14 x=42÷14×100=300 だから 300g
- 12÷(288+12)×100=4 だから 4%
みたいな感じに出ます。
中学生になって文字式を習ったので、覚える公式は1つで済むし、ぐっと楽になりました。
半分ずつ入れ替え
以降は半分ずつくらい入れ替えて、簡単に解ける問題と少し考える問題がセットになるようにしました。
上記の1~3を「またこれー?簡単すぎなんだけど」とか言い出したら半分増やして。
1~3は前日までと全く同じにするからこんな感じです。
- 9%の食塩水300gの中に食塩は何gありますか。
- 42gの食塩で14%の食塩水を作ると、何gの食塩水ができますか。
- 12gの食塩と水288gを混ぜると何%の食塩水ができますか。
- 25gの食塩で5%の食塩水を作るには何gの水が必要ですか。
- 180gの水に20gの食塩を入れて食塩水を作りました。この食塩水と同じ濃さの食塩水240gを作るには何gの食塩が必要ですか。
- 6%の食塩水350gと14%の食塩水450gを混ぜると何%の食塩水になりますか。
そうすると「またこの簡単なやつ」とか言いつつ、最後までなんとか解き。
もし新しく追加された問題が分からなくても、これは初めての問題だし仕方ないと、拒絶反応が少な目になりました。
初めは模範的?な解答でしたが、次第に100を書くのを面倒くさがったりxを省略したりして色々になりました。
- x÷300=0.09 とか 0.09×300 とか
- 42÷x=0.14 とか 42÷0.14 とか
- 12÷(288+12)×100 この100は必要
- 25÷0.05ー25
- 20÷(180+20)=x÷240
- 真面目に塩の量から求めると (350×6+450×14)÷(350+450)×100 ですが
割合に着目して求めるなら 6×350÷(350+450)+14×450÷(350+450)
どちらでも同じ答えになるからOK
食塩水は色々な求め方ができるのが迷うところでしょうか。
理解して解けることが目的なので、かける数とかけられる数の関係とかは気にしていません。
私は初めて見る解き方が出てきたら、時間をもらって本当に正しいのかチェックしていました。
半分ずつだと手が止まるようになったら、今まで解けていた問題に1~2問ずつ難しい問題を取り入れるようにしたり。
難しくなって嫌がってきたら、簡単な問題に戻りました。
進んだり戻ったりして…最終的には最後まで解ききれるようになりました。
数値を変えて立式のみに
初めの数回は答えまで出したのですが。
- 子どもが答えだけを覚えてしまう
- 計算にかかる時間がもったいない
- 数字をいじりにくい
ということで、効率よく食塩水を学ぶために立式だけにしました。
自分で数値を変えたうえで答えまで出させるなら、整数が答えになるように逆算して問題を作る必要があります。
そうするとその時々で適当な数値に変えることができず、面倒です。
でも、立式だけさせたことで、数値を適当に変えても気にしなくて済み、ズルが防止でき、効率もアップといいことづくめ。
印刷する前に変えることもあれば、何枚か印刷しておいて後で鉛筆でササっと数値だけを変えることもありました。
食塩水のプリント
息子が食塩水の苦手を克服するのに使った問題を載せておきます。
答えのみ暗記防止&効率アップのため、立式のみの利用をおすすめします。
問題
1)9%の食塩水300gの中に食塩は何gありますか。
2)42gの食塩で14%の食塩水を作ると、何gの食塩水ができますか。
3)12gの食塩と水288gを混ぜると何%の食塩水ができますか。
4)25gの食塩で5%の食塩水を作るには何gの水が必要ですか。
5)180gの水に20gの食塩を入れて食塩水を作りました。この食塩水と同じ濃さの食塩水240gを作るには何gの食塩が必要ですか。
6)6%の食塩水350gと14%の食塩水450gを混ぜると何%の食塩水になりますか。
7)12%の食塩水と18%の食塩水を2:1で混ぜると何%の食塩水になりますか。
8)8%の食塩水と12%の食塩水を3:1で混ぜた食塩水400gに14%の食塩水100gを混ぜると何%の食塩水になりますか。
9)15%の食塩水200gに水を何gを加えると、10%の食塩水になりますか。
10)2つの食塩水A、Bがあります。Aは12%の食塩水400gで、Bは8%の食塩水300gです。Aに何gの水を入れると、食塩水A、Bの濃さは同じになりますか。
11)6%の食塩水400gから水を蒸発させて8%の食塩水にするには、何g蒸発させればよいですか。
12)食塩15gと水285gを混ぜ、火にかけていきました。
(1)すべて混ざり合うと濃さは何%ですか。
(2)火をかけ続け、水が何gか蒸発したので、濃さを調べたところ、10%でした。水は何g蒸発しましたか。
13)4%の食塩水300gに食塩を2g入れて、火にかけて、水を蒸発させたところ、5%の食塩水になりました。水は何g蒸発しましたか。
14)15%の食塩水180gに食塩を加えて25%の食塩水を作るには、何gの食塩が必要ですか。
15)4%の食塩水300gに食塩を何gか加えたら10%になりました。さらにこの食塩水に15%の食塩水180gを加えたところ、500gの食塩水ができました。この食塩水の濃さは何%ですか。
16)18%の食塩水に水200gを入れると12%になりました。18%の食塩水は何gですか。
17)8%の食塩水に食塩を40g入れると24%の食塩水になりました。8%の食塩水は何gですか。
18)4%の食塩水600gと10%の食塩水を混ぜたところ、7%の食塩水ができました。10%の食塩水は何gですか。
19)10.8%の食塩水と3.6%の食塩水を混ぜたところ、6%の食塩水が600gできました。10.8%の食塩水は何gですか。
20)2つの食塩水A、Bがあります。Aは5%の食塩水200gで、Bは濃さのわからない食塩水300gです。AとBをすべて混ぜ合わせると11%ですが、Bを残して混ぜたので、10%の食塩水ができました。
(1)食塩水Bの濃さは何%ですか。
(2)残した食塩水Bは何gですか。
21)2つの食塩水A、Bがあります。Aは12%の食塩水200gで、Bは4%の食塩水300gです。はじめAの食塩水100gをBに入れてよくかき混ぜた後、Bの食塩水100gをAに入れてかき混ぜました。このときのAの食塩水の濃さは何%ですか。
答え
複数の立式ができるものもあるため、答えはこれ以外も存在します。
実際にお子さんの立てた式が合っているかは、問題を見てチェックしてあげてください。
1)x÷300×100=9 , x÷300=0.09 , 300×0.09 など。
2)42÷x×100=14 , 42÷14×100 , 42÷x=0.14 , 42÷0.14など。
3)12÷(288+12)×100
4)25÷x×100=5
5)20÷(180+20)=x÷240
6)(350×6+450×14)÷(350+450) , 6×350÷(350+450)+14×450÷(350+450) など
7)12×2÷3+18×1÷3
8){(0.08×3÷4+0.12×1÷4)×400+0.14×100}÷(400+100)×100
9)(0.15×200)÷(200+x)=0.10
10)(0.12×400)÷(400+x)=0.08
11)(0.06×400)÷(400-x)=0.08
12)
(1)15g÷(285+15)×100
(2)15g÷(300ーx)=0.1
13)(0.04×300+2)÷(302ーx)=0.05
14)(0.15×180+x)÷(180+x)=0.25
15){0.1×(500ー180)+0.15×180}÷500
16)0.18x÷(x+200)=0.12
17)(0.08x+40)÷(x+40)=0.24
18)(0.04×600g+0.1×x)÷(600+x)=0.07
19)0.108×x+0.036(600ーx)=600×0.06
20)
(1)(0.05×200+0.01×x×300)÷500=0.11→x=15%
(2){0.05×200+0.15×(300ーy)}÷(500ーy)=0.1
21)AをBに入れたときの濃度 {(0.12×100)+(0.04×300)}÷(100+300)=0.06
BをAに入れると12×1/2+6×1/2
まとめ
このくらいまで解けるようになれば、大体の濃度の問題はできると思います。
半年前の全統中の問題であんなに簡単な食塩水の問題を間違っていた息子も、中学生の理科の濃度の問題をラクラク解けるようになりました。
私は初めHello Schoolさんというサイトを参考にし、自分で適当に数値をいじって使いました。
リンクを貼りたかったのですが、上記のサイトは数カ月前から表示されなくなり残念です。
この記事が食塩水を苦手な子の役に立ったら嬉しいです。
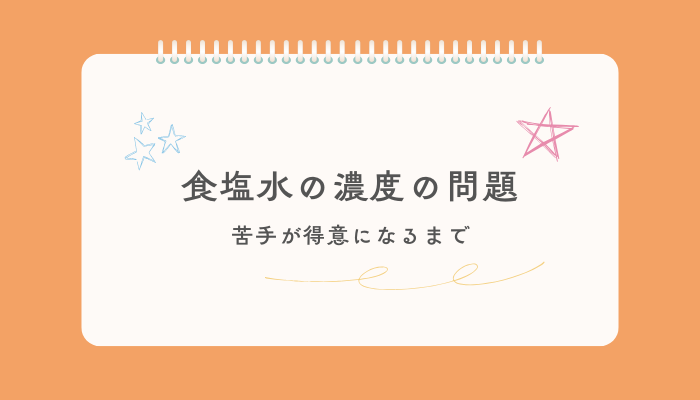
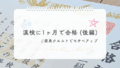
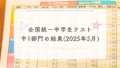
コメント