公立中学校の定期テストは何のためにある?と聞かれたら。
内申点のために点数を稼ぐものでもありますが、年に数回ザックリ分けた範囲の確認をし、間違いから弱点をあぶりだして高校受験に備えるためのものともいえます。
今回は定期テスト(と書き損ねてる全統中)の結果から、弱点やこれからの勉強計画について書きます。
初の定期テストの感想
小学生の頃は5分~多くて30分の勉強が限界だった息子が、定期テスト期間中は凄く頑張りました。
1時間くらいの勉強なら普通にできるようになり、猛烈に文句をいいつつも5時間くらい勉強できる日もあって、凄く成長したと思います。
テスト期間のルーティンや勉強時間についてなどはこちらにまとめてあります。
ただ、反抗期は磨きがかかっています。
例えば、ノートが最終ページだったから新しいのを出してあげたら。

裏表紙の方がいい。ノートにやらせるから分かんなくなった。お母さんのせいで効率が下がった。あーあー!おかーさんのせーでわかんなくなっちゃったー!etc.
とか、吹き出しに入りきれないくらい延々と文句を言われたりします。
ノート出してあげただけじゃん!前のノートと今の解いてる問題は何もつながりないし!裏表紙ならできるってなに!?(心の声)
最近はこの言葉の出番が多いです。

ぐずぐず言うな。
真面目に相手すればするほどヒートアップしていくので、このキメ台詞を言ったらあとは無視です。
って、感想が愚痴になってしまいました。
まぁ、初のテストは息子も私も、お互いにとても頑張ったと思います。
弱点と今後の勉強計画
力を入れる必要がある順に「国語>英語>理科>数学>社会」となりそうです。
軽い方から順に書きます。
社会
テスト結果はケアレスミスだけだったのですが。
ワークの提出が評価「B+」だったので、ワークに力を入れる必要がありそうです。
全部丸付けと赤ペンでの間違いなおしをして、先生が出した加点条件である2回目「+部分」をノートに解いても「B+」とは厳しい。
ワークは全てのページの下にちょこっと書く欄があって、そこにそのページのワーク内容をしっかりまとめる必要があったとのことです。
ちょろっと一言ずつかいてあるくらいでは足りなかったらしいです。
ふくしま式「本当の要約力」が身につく問題集という問題集で要約については何カ月も勉強してきていますが、まだまだ国語力が足りない息子。
社会の勉強法は変えなくて大丈夫そうですが、次からはワークの下の言葉も一緒に考えなければいけなそうです。
数学
定期テストでは100点でしたが、難易度の高い問題が解き足りていません。
定期テストにも問題が出ていた最高水準問題集特進 中1数学を繰り返し解いています。
元々不安があった、計算力の強化も外せません。
毎日12問解いていますが、いまだに12問中1~5問くらい間違います。
最近は「どこが間違ったのか」を毎回書かせる方法を取り入れています。
全統中では塩水の濃度の問題が分からなかったため、定期テスト期間を除いて毎日食塩水の問題を解いてきました。
1ヶ月で食塩水の問題はだいぶ解けるようになりました。
ちょっと難しい「Aの食塩水から100gをBの食塩水に混ぜ、それに塩を5g加えた濃度」みたいな問題もすんなり解けるようになりました。
が!
過程がきちんと書けないため、筆記に不安が残る結果となっています。
式を一切書いていなくて答えだけ当てるため、解き方を息子に説明させると「(食塩水Aに含まれる塩)20gが(Bにうつるから、元々のBの食塩15gと合わせると)35gで、(ここに5gの塩を足したら)40gだから…」って言いたいことは分かるけれど、解答用紙的に×。
これも国語力の問題なのかな?
夏休みには場合の数と確率に入る予定なのだけれど…。
理科
テスト範囲が発表されるより前、準拠ワークを始めてすぐに判明したことなのですが。
息子は学校の授業で習ったことを覚えてきていません。
例えば、「スケッチは細い線で影はつけずに」とノートにも自分で書いたのに。
黒く見えたとかで、レポートに書かれたミジンコのスケッチは真っ黒に塗りつぶされていました。
そのまま出したらアウトなので、もちろん家で書き直させました。
こんな感じの例は、枚挙にいとまがなく。
息子は授業の進みがゆっくりな公立中学校なのに、理科の予習が必要です。
準拠ワークの「教科書ワーク」は、一番簡単なステージ1の下に解答の選択肢が書かれていて、なんとなくこれかな?ってわかるため、予習に使うことにしました。
※教科書に合わせる必要があるので、ネットで買う場合は注意してくださいね。
口頭で一問一答すると私が必ずついていなければいけないため、自分で答えを隠しながら見て解いてもらっています。
英語
息子は英検準2級に合格はしているものの、全く英語の文法が分かっていません。
今まで「中学校で習えば英語の文法はできるようになるだろう」と楽観視してきたからです。
この度、中学校で習っても、英文法はできるようにならないことが判明しました。
定期テストの勉強で準拠ワークを解かせると間違いまくり。
理科で授業内容を全くわかってないところから薄々気づいていましたが、息子の能力を読み間違えていたようです。
英文法は家で教える必要があるようです。
数検3級合格に導いてくれた「中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本 」の英語版問題集を使って、1回目の英文法に入っています。
左が解説、右に問題集のつくりで、問題があるためサラッと呼んで何も頭に残らないってことはないです。
が、間違えまくりです。
それと、英文は丸付けがものすごく大変です。。。
国語
最も力をいれていく予定の教科が国語です。
国語が足を引っ張ってしまっているからです。
基礎的な国語の問題集をいくつか比較して、解説が詳しくてサクッと解けそうなこちらの問題集をやっています。
解説は全ての問題に対してしっかりしていると思うのですが…
国語力の低い息子は、解説を読んでも納得できていないみたいです。
私が解説するのにも限度があるため、筆記に強いと聞くZ会を取り入れてみることにしました。
ちょうど良いタイミングなので、夏休みはZ会にお任せしてみます。
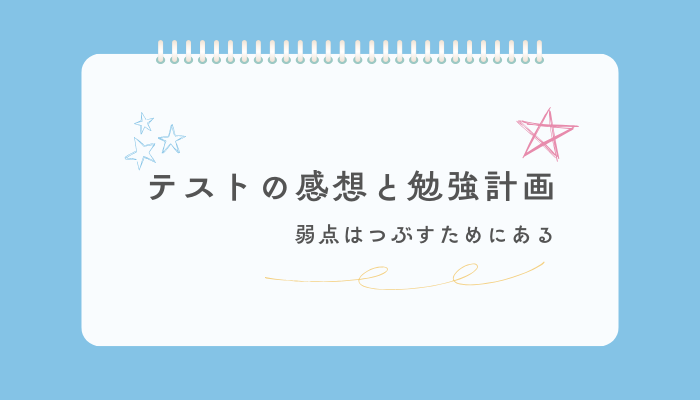
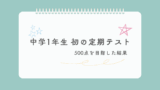






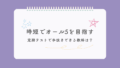
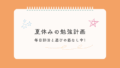
コメント