今回から2回に分けて、息子がやっていた短期間に少ない勉強量で漢検合格した勉強法をまとめます。
あくまで短時間勉強の合格を目標にした勉強法なため、この学び方では級相当の真の実力がつかない!とのお叱りはご遠慮願います。
ポイントは3つ
短期間で合格できたのは、
- 出る問題がまとまったテキストを使い
- テスト中心の勉強法で
- できる限り書かなかった
ことが大きかったと思います。
使ったテキストはこれです。
同じシリーズで漢検3級や4級などのテキストもあります。
「テスト→間違いを覚える」を繰り返しました。
そして、漢字といえば書いて覚えるイメージですが…

漢字書くの?だっるー。やりたくない。
という息子の希望と、勉強時間を短くするために、なるべく書かずに学んでいます。
具体的には、漢検範囲の半分は全く書かずに覚えました。
勉強する順番
発音も意味も分からないと覚えるのに時間がかかることもあり、読みを始めにしっかり学んでいます。
次が、大きな点数を占める、漢字の書き。
そして知っていることのプラスが大きい四字熟語。
重要視している順に勉強したため、こんな順番になりました。
- 読み←全く書かない
- 書き
- 四字熟語
- その他もろもろ←あまり書かない
- 誤字訂正←ほぼ書かない
テキストでの網羅率が低い誤字訂正は試験を申し込んでからちょこっとだけやっています。
テスト流勉強法
漢字を覚えるため、こんな感じに何回もテストしていきます。
- 全問テスト→間違いにマーカーを塗る
- マーカー問題テスト→間違いにふせんを貼る
- ふせん問題テスト→当たったらふせんを外す
- 3のテストをふせんが全部外れるまで繰り返し
私はスピードアップのため、テスト前に必ず

間違った問題は覚えられるまで即テストするよ
と言っていました。
初日からマーカー塗りテスト
覚えている漢字を除いて勉強時間を短くするため、テストから始めます。
息子はつい答えをみちゃったりするので、私が横に座ってテストしています。
私が答えを隠し、息子に漢字を1から順に読み上げてもらいます。
間違っていたら黄色マーカーを塗っていきます。
親子で一緒にやったときは見開き1ページ1分、子ども一人だと3分前後だったため、一緒にやるだけで3倍の効率でした。
このとき、考えこむようならマーカーを塗ります。

コレは知ってた!今言おうとしたのに!
と言われますが、即答できない時点で記憶があやふやなので除外はできません。
漢検は該当級の漢字だけでなく1~2級下の漢字も多いです(2級の読みだと該当級の漢字は20%強)。
なので、たとえばある日の息子の読みの正答率は40%くらいでした。
今後この40%はノータッチになるため、初めにテストするだけで全体的に読みを学ぶのに比べて60%の時間で済む計算です。
テスト直後にふせんテストで周回
テストで間違ってマーカーの塗られた漢字は、すぐに周回です。
マーカーの問題を再テストするとき、間違ったら百均の一番小さいふせんを番号に貼っていきます。
最後まで解き終わったら、ふせんがついた問題を頭に戻ってもう一度解きます。
このとき、当たったらふせんを外していきます。
「これよく覚えたね!」「こんなに当たるのが増えたね!」などポジティブな言葉をかけたり、覚えにくい漢字は助けになりそうな雑学を挟んだりもしつつ。
読みも意味も初めて知る漢字が残りやすいため、「この漢字の意味は?」とか聞きつつ、ふせんが全部外れるまで繰り返しテストします。
2日目からはマーカー周回+ふせんテスト
ごく普通の記憶力の息子は、翌日にはかなり忘れています。
なので、翌日も全く同じマーカーを塗った問題のみをテストします。
マーカーが塗ってない、1回目のテストで正解した漢字は本番前まで放置です。
前日の漢字テストと同じやり方で1周目は間違いにふせんを貼っていきます。
2周以降は当たったらふせんを外し、ふせんが全部外れるまで何周もやります。
初日に比べて2日目の方が全部のふせんが外れるのが早いですし、昨日やった範囲が終わったら、次のページ~の1回目のテストも追加します。
8割方覚えたら新色マーカー塗りテスト
初日に知らなくてマーカーを塗った問題を、ふせんを付けながら何日か周回していると。
だんだん、ふせんを使う数が減ってきます。
8割がた覚えていそうだと思ったら、マーカーの問題を一緒にテストします。
やり方は初日と同じで、間違った問題に新しい色のマーカーを塗ります。
私は初めは薄い色の黄色マーカー、2回目は緑色マーカー、3回目は青マーカーにしています。

2回目テストでマーカーは5つくらいに減った!すごくね!?
だそうな。本人も達成感を味わえてwin-winです。
今回も間違った問題はもう一度周回し、間違ったらふせんを貼り、正解して全てのふせんが外れるまで再テスト。
今後はこの緑マーカーを塗った漢字のみ、周回していきます。
部首はアプリで遊びながら
部首はアプリで遊びながら覚えると早いです。
息子が使っていたアプリを紹介しておきますね。
どちらも広告は出ますが無料です。
一番のお気に入りは漢検漢字・漢字検定チャレンジ。
部首をタイムアタック的に当てていくゲームがおすすめです。
当て続けると、どんどん点数が上がっていって…点数が高すぎる「変人」をはじめ「玄人」「一人前」などの称号もつきます。
初めは間違いまくりでイラついていましたが、何回かやると当たるようになり、短時間で次々に部首を覚えていました。
間違いまくりの時には『漢検〇級 漢字検定問題集シリーズ』も使っていました。
アプリで部首を覚えるのは朝から部活の準備が早く終わって余った5分、ファミレスで運ばれてくるのを待つスキマ時間など、勉強時間外にしていました。
アプリで部首を覚えておくと、受検を申し込む前に1回テキストの部首をテストするだけでほぼ正解します。
間違った部首は黄色マーカーをつけておいて、他の分野を周回するついでにプラスするだけで覚えられました。
読み&部首は書きゼロ
今回は我が家流、テスト勉強法「読み」編と、部首の勉強法を紹介しました。
ここまで、漢字の書きはゼロです。(今回は紹介していませんが、熟語の構成も全く書きません。)
書かずに口頭でテストすることで、漢検の勉強時間を大幅にカットできたと思います。
初日に読みのテストをし、ふせんを使って周回すること5日ほど。
読みを8割がた覚えて、なかなか覚えられない問題には緑マーカーが塗られた頃に、書きに入っていきます。
あ、うちでは進みが悪く感じたときは、朝だけでなく昼や晩も読みのテスト周回をプラスしたこともあります。
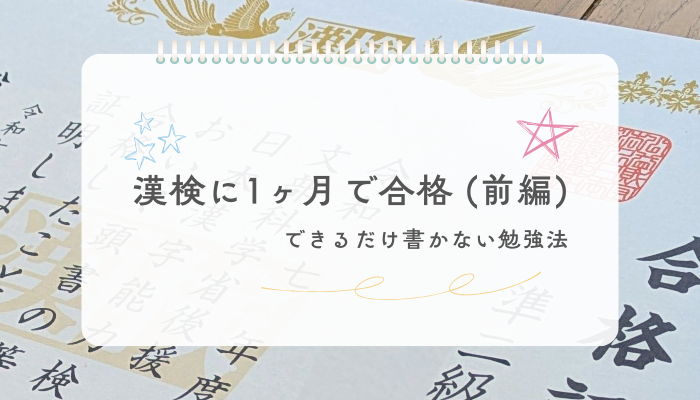



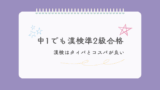
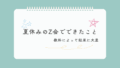
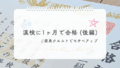
コメント